Webライターのプロフィールは、クライアントが発注先を選ぶ際の重要な判断材料です。プロフィールを改善することで、受注率が大幅に向上したという声も多数見られます。
しかし、Webライターの「良いプロフィール」と「悪いプロフィール」の違いは何なのか、よくわからないという人も多いでしょう。良いプロフィールを作成できれば、そのまま名刺代わりとなって仕事の受注につながります。
本記事では、Webライターのプロフィールを構築する方法を具体的に解説します。読みながら実践できるワークもつけていますので、仕事を取れるプロフィールを手にするためにぜひお役立てください。
なぜWebライタープロフィールで仕事が決まるのか?
Webライターブログやクラウドソーシングサイト、SNSアカウントなどのプロフィールは「オンラインの名刺」。つまり、自己紹介を担う重要なアイテムです。
仕事を受注するためには、クライアントの第一印象に気を配る必要があります。
クライアントがチェックするプロフィールの3つのポイント
特にクライアントが重視するのが、以下3つの点です。
- 信頼性(実績・経歴)
- 専門性(得意分野・スキル)
- 相性(コミュニケーション能力・人柄)
これらの項目について、わかりやすく明確に伝わるようなプロフィールを打ち出すことで、仕事の受注や人脈の広がりにつながっていきます。
プロフィールは受注率に及ぼす?
プロフィール改善による効果について、具体的なデータは見つかっていませんが、「受注率がアップした」「適切なプロフィール写真に変更したら、返信率が高まった」といった報告も見られます。
適切なプロフィールは自己成長に直結する
丁寧に作り上げられたプロフィールは、自分が「何をする人なのか」「どういう立場の人にどのような価値を提供できるのか」といった役割を客観的に示します。
そのため、自分が目指すキャリアや将来のゴールの再確認という意味でも役立ちます。
ただ、自己成長につながるプロフィールを作るためには、自分の価値を正確に把握する必要があります。
自己分析を飛ばしてしまうと、自分に合わない分野や業界で営業して仕事を受注できない、という状況に陥ってしまう可能性があります。
質問1:これまで執筆した記事ジャンルをすべて書き出してください
質問2:クライアントから褒められた点を3つ挙げてください
質問3:他のライターと差別化できる要素は何ですか?
質問4:なぜWebライターになったのですか?経緯を簡潔にまとめてください
質問5:1年後のライターとしての目標は何ですか?
【ワーク1】自己分析からキャッチコピーを作る3step
プロフィールの冒頭1〜2文で、読む人の興味を引きつける必要があります。Webライターのキャッチコピーをつけることで、「何ができる人なのか」が一目で伝わります。
ここで紹介する「キャッチコピーの作り方3ステップ」に沿って考えることで、自分がどういうWebライターなのか、明確に伝えられるキャッチコピーを作成できます。
step1:強み要素の優先順位づけ
以下の質問1〜5は、プロフィール作成に役立つ自己分析の質問です。「最もアピールしたい要素」を1つ選びます。
まずは、「売れるプロフィール」の材料を集めるための質問を紹介します。以下5つの質問に率直に答えてみてください。回答は、後でプロフィールに直接活用できる形で記録しましょう。
質問1:これまで執筆した記事ジャンルをすべて書き出してください
質問2:クライアントから褒められた点を3つ挙げてください
質問3:他のライターと差別化できる要素は何ですか?
質問4:なぜWebライターになったのですか?経緯を簡潔にまとめてください
質問5:1年後のライターとしての目標は何ですか?
すべての質問に回答してから選んでもいいですし、1つの質問に絞っても考えても構いません。クライアントニーズとの適合性を考慮して選ぶと、仕事の受注につながります。
step2:キャッチコピーのパターン選択
キャッチコピーにはいくつかのフォーマットがあります。Step1で選んだ自分の強みを当てはめやすいパターンで作ってみましょう。
- 実績型
-
実績が豊富な人が信頼性と安定感をアピールする
例:「○年で○○記事執筆、継続率○○%」 - 専門性型
-
特定業界の経験がある人が権威性と専門性をアピールしやすい
例:「元○○、専門知識を活かした○○記事が得意」 - 組み合わせ型
-
複数スキルの組み合わせができる場合に希少性と付加価値をアピールできる
例:「○○もできるWebライター」 - ストーリー型
-
共感性と親近感をアピールして感情的なつながりを重視できる
例:「○○の経験から○○を伝えるライター」 - 成長型
-
初心者でも意欲や熱意、将来性をアピールできる
例:「○○を目指すWebライター」
step3:キャッチコピーのブラッシュアップ
キャッチコピーは、端的でわかりやすいことを優先します。文字数が多い場合はカットして調整しながら、読みやすい表現に修正しましょう。
例1:元営業マン(営業10年、転職系記事得意、提案力が強み)
「営業経験10年、転職記事が得意なWebライター」
→「元トップ営業マンが書く、内定に繋がる転職記事」
例2:子育てママ(育児中、美容・子育て記事、丁寧さに評価がある)
「子育て中、美容・育児記事が得意なWebライター」
→「現役ママ目線で共感を呼ぶ育児・美容記事」
キャッチコピー作成時の注意点
たとえ事実であっても、誇大表現は避けるべきです。「業界No.1」「100%」といった表現は、誤解を生む可能性があるため、クライアントとの関係構築を意識して別の表現に変更した方が良いでしょう。
また、ターゲットの業界やジャンルのクライアントを意識した言葉選びも重要です。加えて、数値や実績など具体性を重視し、「豊富な経験」ではなく「5年の経験」と記載します。
プロフィール構成の黄金パターン
プロフィールは営業資料として機能させることが大切で、クライアントが最低限知りたい情報を過不足なく配置する必要があります。
プロフィールの構成の基本パターンを使うことで、必要な情報を網羅しつつ、すっきりと読みやすくまとめることが可能です。各セクションで書く内容や目安の文字数についても詳しく説明します。
プロフィールの基本構成【テンプレート】
・キャッチコピー(冒頭の一文)
・専門分野・得意ジャンル
・実績・経歴
・提供価値・クライアント側のメリット
・人柄・信頼性
・連絡・対応について
※各セクションは重要度順に配置します
キャッチコピー(冒頭の一文):30文字
アイキャッチの部分は、クライアントの第一印象を決める最重要の要素です。
キャッチコピーがあると、相手が抱くイメージの解像度をぐんと高めることができます。直接的にどういう仕事をする人なのかを伝えることで、一気に興味関心を引くことができるため、自分の強みを端的に表現すると理想的です。
例えば「納得できるまで修正依頼OK!」「2,000文字までなら2日以内に納品」など。
専門分野・得意ジャンル:50文字
具体的なジャンル名を箇条書きで記載します。「なんでも書けます」よりも、自分の専門分野や得意なジャンルを記載した方が、クライアント側が依頼するかどうか判断しやすくなります。
実績・経歴:100文字以内
実績は、Webライターとしての信頼性の根拠となるため、担当した記事数やクライアント数などの数字は必ず明記します。専門分野での職歴や経験年数、継続案件の数などもOKです。
提供価値・クライアントメリット:80文字
他のライターとの差別化ポイントとなるため、「自分に依頼する理由」を明確に言語化します。Wordpress入稿など、具体的な付加価値サービスがあればそちらも記載します。
人柄・信頼性:70文字
レスポンスの速さや納期管理、コミュニケーション能力など具体的な対応スタンスを明記します。「一緒に働きやすそう」「相性が良さそう」という印象を与えられる表現が理想的です。
連絡・対応について:40文字
迅速に連絡が取れる手段を明記します。返信時間や対応可能時間帯(例:平日9時〜18時まで)に加えて、SlackやChatworkなど使用可能なツールも明記します。(緊急時の連絡先として、共有できるものがあるとベター)
【ワーク2】魅力的な冒頭文の作り方
プロフィールの冒頭1〜2文で、クライアントは読み続けるかどうかを判断します。良い印象を持ってもらうための具体的な書き方やテンプレートについて見ていきましょう。
インパクトのある冒頭文パターン5つ
相手に良い印象を与えるためのインパクトのある冒頭文には、主に以下のパターンがあります。
・実績特化型:具体的な数字や成果
・ストーリー型:人間味や信頼性
・問題解決型:具体的な問題解決の経験や手法
・専門性アピール型:権威性や希少性
・人柄重視型:安心感や継続性
パターン選択のおおまかな基準
- 初心者(0〜1年):ストーリー型、人柄重視型
- 中級者(2〜4年):実績特化型、専門性アピール型
- 上級者(5年以上):問題解決型、実績特化型
【穴埋めワーク】冒頭文作成ワーク
上記をもとに、以下の穴埋めを使って冒頭分を完成させてみましょう。
私は[専門分野]に特化したWebライターで、
[最も強いアピールポイント]を活かし、[クライアント]の[解決したい課題]を
[強み・手法・スキル]でサポートします。
冗長にならないよう、文字数は30〜50文字に調整します。また、読みやすさを重視し、ひらがな・カタカナ・漢字のバランスに違和感がないか、チェックしておきましょう。
【ワーク3】クライアントの心をつかむ「提供価値」の書き方
クライアントが「あなたに仕事を依頼するメリット」を明確にわかりやすく示す必要があります。
単なる「できること」の羅列では差別化にならないため、クライアントの課題解決の視点を持って、価値を表現することが重要です。
クライアントの心を掴むための具体的なまとめ方のポイントについて説明します。
「できること」より「解決できる課題」を書く
課題解決の視点を持つことで、自分が「何ができるのか」よりも、クライアントに対して「どういう価値を提供できるのか」をはっきり示すことができます。
クライアントの抱える課題や痛みに直接アプローチして、解決できる、という具体的なイメージを提供できるからです。
多くのライターのプロフィールには実績や経歴があっても、クライアント側へのメリットを深く考えてまとめている人はそう多くないため、競合と差別化できます。
また、ここまで述べてきたプロフィールの他の要素と相乗効果により、信頼性を得られ、高単価案件の獲得にもつながります。
・クライアント業界のトレンドを調査
・競合他社の分析から課題を推測
・過去の案件でクライアントが困っていたポイントを整理
・業界特有の悩みをSNSやフォーラムで収集
従来の書き方(NG例)
「SEOライティングができます」
「WordPress入稿ができます」
「取材記事が書けます」
価値重視の書き方(OK例)
「検索順位低下によるアクセス減少をSEOライティングで改善します」
「WordPress直接入稿で更新作業の負担を軽減します」
「商品の魅力が伝わらない問題を取材記事で解決します」
業界別クライアントの悩みと解決策の提示方法
ここでは、以下3つの業界をピックアップして、よくある課題と具体的な解決策の提示サンプルを紹介します。
- 不動産業界
- 金融・保険業界
- IT・SaaS業界
不動産業界
- 主な悩み
-
- 物件の魅力が文章で伝わりにくい
- 法的規制が多く専門知識が必要
- 地域情報の収集・発信が困難
- 顧客の不安解消ができていない
- 解決策の提示方法
-
- 「宅建資格保有による正確な法的情報の提供」
- 「現地取材による詳細な地域情報記事の作成」
- 「購入・賃貸時の不安を解消するQ&A記事の制作」
- 提供価値の例文
-
「物件の魅力不足を現地取材と宅建知識で魅力的な紹介記事に変換」
金融・保険業界
- 主な悩み
-
- 複雑な商品内容を噛み砕いて説明できない
- 信頼性・権威性が重要で、素人では難しい
- 法的規制(薬機法等)への対応が必要
- 顧客の不安を解消する説明力が求められる
- 解決策の提示方法
-
- 「FP資格を活かした専門的かつわかりやすい解説記事」
- 「複雑な保険商品を図解と事例で理解しやすく説明」
- 「法的規制を遵守した安全な記事制作」
- 提供価値の例文
-
「複雑な金融商品を顧客目線でわかりやすく解説し成約率向上」
IT・SaaS業界
- 主な悩み
-
- 技術的な内容を専門知識がない人に対してわかりやすく説明できない
- 競合商品との機能比較が複雑
- 導入効果を具体的に示せない
- 最新技術の情報収集が困難
- 解決策の提示方法
-
- 「元エンジニアの技術知識で正確かつわかりやすい解説」
- 「実際の導入事例を交えた具体的な効果説明」
- 「技術トレンドを踏まえた最新情報の提供」
- 提供価値の例文
-
「複雑なIT商品を非技術者にもわかりやすく説明し導入促進」
【穴埋めワーク】提供価値文の完成
[ターゲット業界]の[具体的な課題]に対して、
[あなたの専門知識・スキル]を活用し、
[期待できる成果・効果]を実現します。
記入例(EC業界の場合)
EC・通販業界の「商品の魅力が伝わらず売上低迷」という課題に対して、
「元販売員の接客経験とSEOライティングスキル」を活用し、
「購買意欲を刺激する商品記事による売上20%向上」を実現します。
信頼性を高める要素の盛り込み方ポイント
資格・認定の効果的な書き方
資格や認定は、業務にどのように役立つかを具体的に示すことが大切です。
宅建士や税理士など難関資格や、独占業務のある国家資格は、保有しているだけで大きなアピールポイントになります。専門知識や実務経験を経て、資格試験に合格した優秀な人材として、市場における希少価値が高いことの裏付けとなるからです。
Webライターとして活躍する上でも、有力な資格があると専門分野を確立しやすく、高単価案件や継続案件の受注にもつながるでしょう。資格や認定を使った経験や実績をどのように記事作成に活かせるかもまとめます。
【経験年数別】実績・経歴の効果的な見せ方
- 初心者(〜1年)
-
- 学習意欲と誠実さ、稼働時間などをアピール
- 資格・研修受講の活用も考慮
- 他業界経験の転用
- 中堅ライター(2〜5年)
-
- 専門性に沿った実績を厳選
- 継続案件・リピート率の強調
- 専門性の深掘り
- ベテランライター(5年以上)
-
- 地位・影響力のアピール
- メンタリングや指導の経験◎
- 独自のノウハウも可
読みやすさを向上させる工夫
プロとしての信頼感を損なわないよう、誤字脱字のチェックはしっかりと行いましょう。改行を効果的に使用しつつ、情報量が多くなりやすいときは箇条書きで整理すると読みやすくなります。装飾や記号(■、・)を使うと、視覚的にメリハリをつけられます。
また、ダラダラと書かず、冗長な部分は要約することも大切です。読みにくいと、効果的にアピールできず、受注率の低下にもつながります。
顔写真や本名使用のメリット・デメリット
ブログやSNSのプロフィールで顔写真や本名を公開すれば、客観的な信頼性が向上するため、案件獲得につながる可能性があります。
ただし、誰でも気軽に使える場面で公開することに抵抗を覚える人は、似顔絵や親しみやすいニックネームを使い、正式に契約する際に本名を伝える方法でも問題ありません。
わたし自身は、クラウドソーシングサイトやSNSにも顔写真や本名を登録したことはありません。専門性を決めかねていたために、ズルズルと雑記でやってきたというのもありますが、顔写真=受注率とは言えないというのが経験上の意見です。ただ、建築業界の専門性を活かせば違う経歴になったかもしれない、と振り返ることはあります。基本的には、雑記ライターより専門ライターを推奨しますが、実際には実践的な情報や経験からくる深い情報をどれだけ活用できるかが重視されていくと考えます。
よくあるプロフィールの失敗例と改善法
プロフィール作成でWebライターが陥る3つの典型的な失敗パターンを紹介します。失敗例を知ることで同じミスを回避し、受注率向上につなげることが可能です。
失敗例1:専門性が伝わらない抽象的な表現
専門性を伝える際には、クライアントが具体的な能力を判断できるよう差別化することが重要です。複数の強みがあるからといって、すべてについて詳しく記載しても「どれが専門なのか」がわかりにくくなってしまっては意味がありません。
また、経験についても同様に、抽象的な表現は避けて具体性を意識しましょう。
よくある失敗表現
- 「幅広いジャンルに対応できます」
- 「質の高い記事を執筆します」
- 「SEOに詳しいです」
- 「丁寧な文章を心がけています」
- 「様々な経験を活かして執筆します」
改善方法と具体例
・「幅広いジャンルに対応できます」→「金融業界5年の経験を活かし、投資・保険・ローンの専門記事を執筆。FP2級資格保有。」
・「SEOに詳しいです」→「検索順位1〜3位獲得記事を20本以上執筆。キーワード選定からリライトまで対応可能。」
・「質の高い記事を執筆します」→「クライアント満足度95%を3年継続。」
専門性を具体化するコツ
数字を使った実績や、資格・認定、専門ジャンルや特化している業界を明記する際に、過去の事例について簡潔な説明を添えると親切です。
失敗例2:クライアント視点の欠如(自分本位な内容)
クライアントにとってのメリットがあいまいだと、受注につながりにくくなります。また、プロとしての責任感や課題解決意識が感じられないと、クライアントは仕事を依頼する意味がないと判断してしまうでしょう。
よくある自分本位な表現
- 「ライティングスキルを向上させたいです」
- 「経験を積ませていただきたいです」
- 「初心者なので勉強したいです」
- 「自分の成長のために頑張ります」
改善方法と具体例
「ライティングスキルの向上を目指したい」→「貴社の売上向上に貢献できる魅力的な商品紹介記事を執筆します」
「経験を積みたい」→「貴社のブランド価値向上と読者満足度アップを実現します」
「副業として取り組んでいます」→「限られた時間で最大の成果を出すため、効率的で質の高い記事制作に取り組んでいます」
クライアント視点に変換するコツ
「私は」ではなく、「貴社の」「読者の」へ主語を変更して考えます。自分の利益ではなく、クライアントの利益は何かを明確にし、具体的な貢献方法を説明します。具体的な成果にフォーカスした表現と、プロとしての責任感を示す言葉を選ぶことが重要です。
副業として受注することは事前に伝えるべきではありますが、副業だから優先順位が低いのでは?と思われない工夫が必要です。
失敗例3:ネガティブな印象を与える表現
ネガティブな表現は、クライアントの不安を増大させる恐れがあります。また、プロフェッショナル感が欠けて見え、他の候補者と比較された際に不利になるため、読んだときの印象を確認することが重要です。
よくあるネガティブ表現
- 「初心者ですが頑張ります」
- 「まだ実績は少ないですが」
- 「経験不足で不安ですが」
- 「○○はできませんが」
- 「完璧ではありませんが」
ポジティブ変換の具体例
「まだ実績は少ないですが」→「これまでの○○業界経験を活かし、専門性の高い記事を提供します」
「○○はできませんが」→「○○が得意分野です」(できることだけを記載)
「経験不足ですが」→「丁寧なリサーチと細やかな配慮で高品質な記事を制作します」
ポジティブ変換のテクニック
どのような人なら、クライアントが安心して仕事を依頼できるかを考えてみましょう。「できない」ことは書かず、「できる」や「強み」にフォーカスすることで、「この人ならこの仕事を要求通りにこなせそう」という印象を伝えられます。
また、成長意欲や適度な自信をポジティブな表現で示すとともに、具体的な行動や実績となる記録があると説得力が高まります。
プロフィール完成後の効果測定と改善方法
プロフィールを完成させた後は、定期的に効果を測定し、必要な改善を行いましょう。
完成度を高める見直しポイント
- 自分のスキルが業界の課題解決に適しているか
- 期待する成果が数値化・具体化されているか
- 競合ライターと差別化できているか
- クライアントが「この人に依頼したい」と思える内容か
定期的な見直しタイミング
- 基本的なメンテナンス:月1回
- 大幅な見直し:四半期(3ヶ月)ごと
- 大規模リニューアル:年1回
上記以外に、成果が低下した場合の緊急見直しも効果的です。
また、以下のような環境変化に応じた見直しも適宜取り入れることを推奨します。
- 新しい実績・資格を取得した場合
- 得意分野を変更・追加した場合
- 連絡先や連絡手法の変更
- プラットフォームの仕様変更
まとめ
プロフィールはキャリアアップの秘訣とも呼べる重要な要素です。自己分析の結果を反映して、客観性と説得力のある内容に仕上げることで、受注率アップにつながります。また、継続的な更新と改善によってブラッシュアップすることで、自己成長やキャリアアップを目指せます。
今回紹介したワークを参考にして、Webライター活動を後押しするような自分らしいプロフィールを作成しましょう。
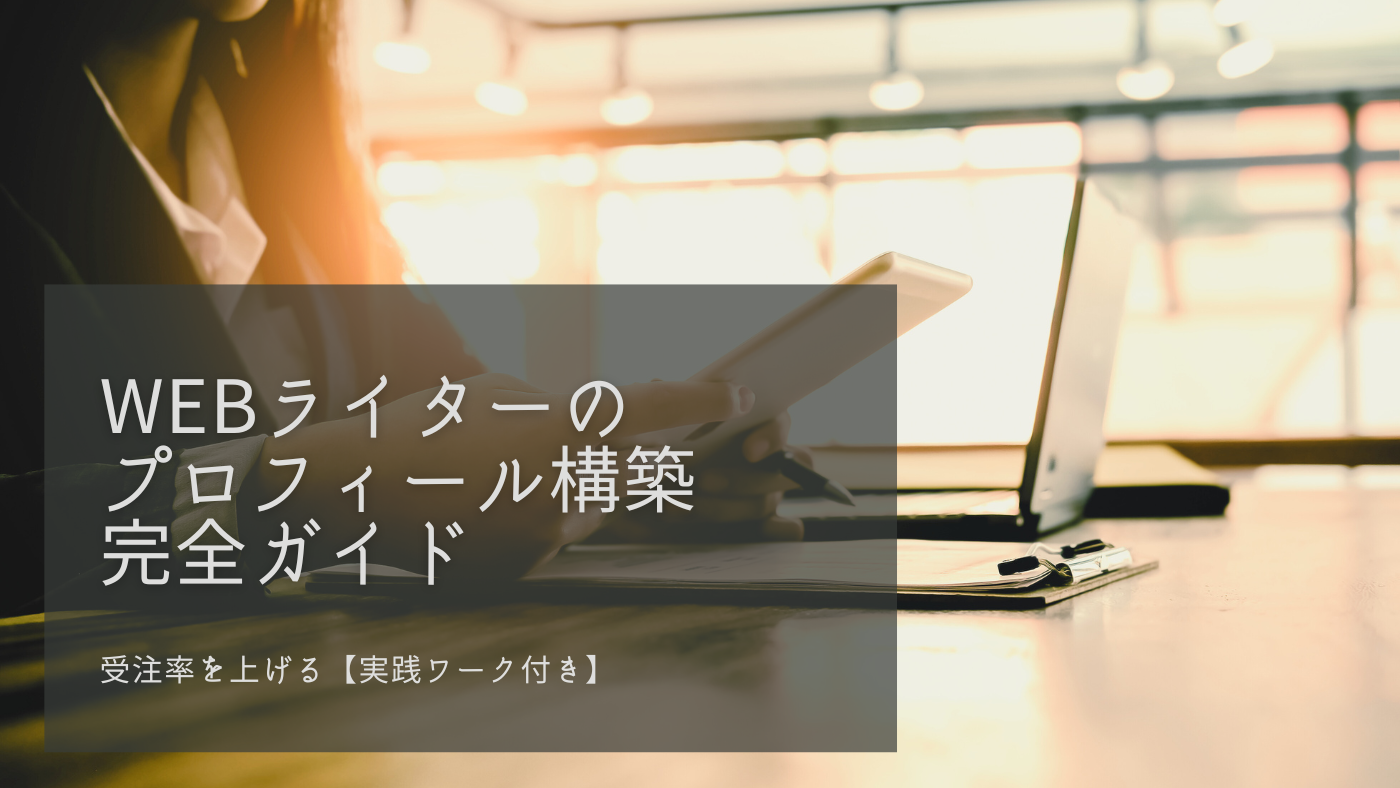

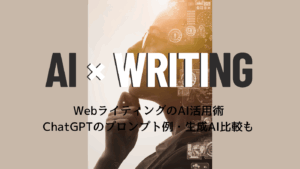

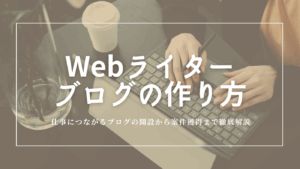
コメント